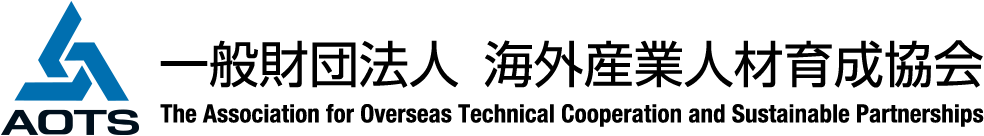|
Contents |
一般社団法人 中部産業連盟
理事 福山 穣
為替相場と人材不足 (1)
しかし不安定な原油価格、中国・米国経済の減速を中心とするグローバルな経済環境、また欧州の難民問題と不安定が拡散する中東の政治環境等を背景に、日本の企業が安心できる状況にあるとはとはいいがたい。不確実性が拡大あるいは拡散しているのが現実だ。2011年の東北大震災や2016年4月の熊本地震による被災は、想像を絶するものであった。
昨年の熊本地震では、米国はいうまでもなく、欧州・アジア等から500億円を超える義援金や救援金が短期に送付されただけでなく、バングラデシュ等の途上国から支援を受けたことに、われわれ日本人は厚くお礼を申しあげたい。同時に、復旧のための協力をいただいているアジアを中心とした外国人ボランティアに対しても感謝したい。
近況を別にするとしても、日本経済は本質的な問題に直面している。それは、まず日本企業が慢性的な人材不足に悩まされていることと、今後も悩まされていくことである。次いで、為替相場の不安定を中心に、日本経済の産業構造そのものを揺るがしていることに要約できる。
アベノミクスに、効果があったことは事実である。しかし、少子高齢化と人口減少、それに伴う国内市場縮小そして国家歳入不足は、日本経済全体だけでなく社会全体の環境変化を引き起しつつある。零細企業や中小企業、とくに家族経営の商店等では、明らかに事業継続が危ぶまれる状況が全国的に起きている。大手企業では「人手」不足というより、「人材」不足という状況に直面しつつある。
人手というのは労働力全体の「数」的な問題であり、人材というのは労働を担う人の「質」的問題である。少子高齢化で国内市場が縮小するだけでなく、事業を担うべき人材不足が多くの産業で目立ちつつある。数の低下が質の低下に結びつくのは理論的に明らかだが、問題はこれまで日本経済を支えた高品質や高い信頼性への疑問にもつながりつつある点であろう。
為替相場の不安定は、たしかに円安で輸出の好調になったものの、逆に円安の影響で電力等のエネルギー・石油関連で原価が上がり、利益率を低下させた。また輸出に関連しない中小企業等では利益が出ず、原価率が悪くなるだけになっている。結果として、これまでの大企業と中小企業によるウイン-ウインの協働作業という日本の産業構造の美点が崩れ、富の配分がいびつになった。
この人材不足と産業構造の変化は、伸ばすべき産業とそれを推進するべき人材との間のバランスをさらに崩すことにつながる。国など行政だけでなく個別企業が、これらを克服してこそ、日本の活路が開けるはずと要約したい。
為替相場と人材不足 (2)
日本のおかれる状況から、どのように活路を切り開くべきかについてのヒントを考えてみたい。
3年前まで、輸出製造業は円高の悪影響を嘆いていた。一昨年末は、ドイツのフォルクスワーゲンの排ガス対策に関する不正がかまびすしかった。「会社ぐるみ」の対応と思われ、世界一の自動車販売金額の企業に対する称賛が一転したものの、それらは他国の話と日本では考えていた。
現在は、どうであろうか。国内大手電機会社の業績嵩上げ、マンション基礎工事の虚偽、さらには日本の自動車会社の排ガス不正と、日本の品質や信頼性にも黄信号が灯った。円安基調は一時的に円高に変化したが、それは諸刃の剣にもなっている。直接輸出がない中小企業には、円安メリットが少ないことは前回も触れた。
数年前から期待された外国人介護・看護士の参入拡大も、期待どおりに進んでいない。漢字が読めないせいでなく、円安のせいで彼らの自国換算での収入が減るため、来日して日本で働くメリットが少なくなっていることが最大の理由とはいえないか。漢字にルビを振り支援しても、金銭には勝てない。強いドル獲得のため米国等へ流れる傾向がある。外国人への日本円による賃金支払いは、ドルや自国通貨ベースでの価値が、かつての6-7割程度に減価することになる。
訪日客は増えても、サービスが人によってなされる以上、良質な人材の不足は国が目標とする年間2000万人の達成にも困難が生じるのではないか。好調といわれる建設や自動車関連の産業でも、同じようなことが容易に起こり、品質や生産性の低下につながりかねない。要は、円安はよくて、円高はまずいではない。ほどよくバランスしてこそ、輸出型の企業も国内依存企業も利益のでる構造となる。
日本企業は、1980年代に製品の高品質さで世界に名だたる地位を築いたが、現在では、製品コンセプトのズレによる開発や、マーケティングのミス、また肝心のものづくりそのものにおいてさえも、世界の動きについていけない。経営戦略、コンプライアンス、社員の活性化と課題は山積みである。このような側面はすべて人によりかかっているのであり、良質の人材の供給があってこそ可能である。にもかかわらず、現状では人材不足や産業によっては枯渇というような状況が起きつつある。
われわれには、自らの姿の再確認が出発点であろう。一面の真理ではなく、複数の側面からの真理をバランスよくとらえる必要があるだろう。円高と円安のメリットとデメリットを両天秤で考えてみる。メリットとデメリット、さらに両者のバランスをとりつつ自社の基本戦略を練り直す必要に迫られているのが、現状の最大課題といえるのではないだろうか。産業構造全体の転換は、自社の責任ではないが、人材の確保は自社の最大の課題となりつつある。
と同時に、海外の皆さまには、日本という市場と、また海外展開にしか活路がない日本企業とのウイン-ウインの関係づくりという明確なターゲットが生じていることになる。
為替相場と人材不足 (3)
これまでの2回にまとめたような背景から、日本企業は大合唱で「生き残り」や「継続」を標榜している。前者の生き残りは、より強化された「勝ち残り」といえるかもしれない。後者の継続は、たんなる存続ではなく、自社技術や技能を継承しつつ、さらなる高みを目指すというものである。
もちろん大企業と中小企業とにちがいはある。大企業は、円高メリットで海外企業の買収を積極化するような傾向がある。海外展開そのものについても、基本戦略を練り直しているようであるが、ここでは日本企業の9割を超える中小企業に焦点を合わせてみたい。
1970年代以降、日本企業はまず「効率化」を目指した。ムダ・ムラ・ムリを徹底的に排除して、品質を高め、生産性を高めようとした動きである。この活動は、80年代に日本企業を、さまざまな分野でまさに “Japan as No.1”にした。しかし、80年代になるにつれ主眼は、活性化に移った。活性化とは、イキイキと仕事をするということで、代表例としてはTQCやTQMの活動が挙げられる。
とりわけボトムアップによる職場をあげての全員参加の活動は、日本製品の品質や生産性を画期的に高め、世界中に日本製品の優秀さや背景である日本的経営を幅広く伝えた。日本的経営は、終身雇用、年功序列(の賃金制度)、企業内組合を3大要素として、企業内における人材のキャリアアップを容易にして、結果として企業レベルで品質向上や技術革新につながるようなシステムであった。
ところが、90年代のバブル経済崩壊後、日本経済は「失われた」10年間あるいは20年間といわれるような、長く続く苦境に直面した。この間、米国や欧州は、IT革命や金融改革によって興隆を取り戻したのに対して、日本経済は失意の期間を迎えることになる。そして、いま現在もその延長線上にあるのかもしれない。
この時代、多くの日本企業は、「創造化」すなわち他社では真似のできない技術や事業や製品を目指す「オンリー1」を追求した。他社が製造できなければ、当然、自社が利益をあげることができる。これらの代表例は青色LEDやハイブリッド自動車であるが、当初期待したような「わが社だけ」の技術や利益は長く続かなかった。多くの国々にキャッチアップされているのが現状である。
このように、ここ半世紀を振り返ることができるが、21世紀の日本企業は、とくに中小企業ではなにを目指し、どうありたいと希求しているのだろうか。そのビジョンは明らかでない。20世紀末から、確実にグローバル化の流れが強まっている。国内市場だけでなく、世界中が一体となった新しい市場で、どう存在感を高めることができるのかが大きな課題となりつつある。
少なくとも、「日本だけよければ」という孤立主義や単独優位を念頭におくのは、どう考えても時代の流れに則していないし、すでに日本が優位性のある産業分野は限られている。世界の中の日本という、われわれの位置づけを明確にしておくことこそが出発点である。
具体的に、どうしたらよいのか。まずグローバルで共生できるように、ビジョンを明確にすることである。わが社は、どこをターゲットとして製品やサービスを提供するのか。製品開発は、国内市場だけを対象とするのか、あるいは世界中の市場を対象とするのか、はっきりさせることである。事業にどのような姿勢で取り組むのか、さらに人材に対してビジョンを明らかにして、多くの関係者から共感を得る必要がある。
国内では、明らかに人材不足である。頭数をいうのではなく、例えば管理職でも、必要な質の人材を確保できないのが現状である。ここ10年の間に多様な人材を確保する、外国人を含めて国内へのある程度の流入を許容していかざるをえないのではないか。製品開発から製造、販売そして管理面にいたるまで、外国人の力を借りていかざるをえない時代となるように思われる。
しかし、それには工夫が必要である。場合によっては、これまでの長期雇用(その最たるものが終身雇用制度)を前提とする各種の人事諸制度を見直す必要があるのかもしれない。そうでないなら外国人だけでなく、日本人すら定着が不可能になる部分がある。
日本人を対象とした、これまでの社内での人材育成も困難になりつつある。しかしながら、比較的長期雇用を前提とした社内における人材育成は、日本企業の強みを裏づける根源ではあった。これは、大企業と中小企業共通の課題である。
この課題の解決には、適正な業務遂行を目指して、上司と部下がよく話し合い、課題を明確にして、達成基準を合意する。適正な目標が選択され、かつ目標値についてきちんと合意する。関連事項については、よくコミュニケートする(双方向での十分なやりとり)。このようにシステム的に対応して、はじめて適正な水準で、業務遂行がなされるはずだ。
筆者の所属する中産連は1993年に『検証 日本の賃金』(日刊工業新聞社)を著し、21世紀をにらんだ新たな人事制度づくりについての提言をした。「組織の中で個性を発揮し、柔軟な頭脳と行動力で、その組織を活性化させる革新的社員」を求めるとして、「ワーカー意識・感覚・発想」から「メンバー意識・感覚・発想」そして「オーナー意識・感覚・発想」への転換を促進させる人事諸制度づくりを目指すとした。
制度づくりの具体的な方向性は、(1) 新たに「期待される企業人像」の多様化、(2) 多様化に対応する個人別の採用から評価・能力開発・処遇にいたる個人別アプローチの必要性、(3) 個人別「方針・目標管理制度」と育成・評価までの連携、(4) 根幹となる「職能資格制度」の質的転換、(5) 一律「相場主義」からの脱却、と時代を先取りした内容であった。
提言どおりこの20年間で、ワーカー(「いわれたこと」を実施すればよしとする被指示者的)意識からオーナー(自ら主体的にとりくむ「当事者」)意識を持つ人材の育成がすすみ、企業の業績向上につながったか客観的に評価いただきたいと思う。と同時に、これまでのチームプレーをどのように維持していくのか、大きな課題が残されている。
為替相場と人材不足 (4)
日本企業がグローバルに共生するには、人を活かし、総合的な観点から、つまりシステム的な諸制度づくりが必要であり、これを人材活用の総まとめとしたい。
これからの人事諸制度づくりは、基盤系を核に、人材開発、評価、処遇、課題解決の各系統をよく連携させ、機能させることが必要である(図参照)。
基盤系は、職群やコース区分、職能資格制度のような能力基準から役割の明確化までをいう。企業(組織)の人事基本方針や人材ビジョン・人事制度ビジョンなど人を活かすための考え方が明確にされるべきであろう。処遇系は、賃金、資格、職位(ポスト)上の待遇である。社外からは、この面だけが企業の魅力と映るが、それは表面的でしかない。